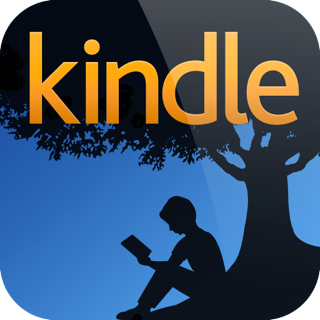「鑑みる」という言葉があります。
近年、この言葉を「考える」という意味で使っている人が増えています。国会の答弁などで政治家が口にしているのを聞くことも多いので、この言葉を「考える」のフォーマルな言い方、「格式高いバージョン」だと思っている人も多いようです。ですが、「鑑みる」という言葉の意味は「照らし合わせる」であり、「考えてみる」ではありません。
「鑑」の語源は「鏡」と同じ
「鑑」は印鑑の「かん」ですが、それ一文字で「かがみ」とも読み、規範や手本という意味を表します。例えば、「彼は独身男性の鑑(かがみ)だ」といった使い方をします。語源は「鏡」と同じです。この「鑑」を動詞にしたのが「鑑みる」で「かんがみる」と読みます。元々は「かがみる」だったのが変化して、こう読まれるようになりました。
かんが・みる【鑑みる】
〔「かがみる(鑑)」の転〕
先例や規範に照らし合わせる。他を参考にして考える。「先例に ─・みて…」「過去の失敗に ─・み…」(『大辞林』三省堂)
ところがこれを、単に「考える」という意味で使うケースが多いと、ネットで話題になっています。
「〜に鑑み」が正しく、「〜を鑑み」は間違い?
ネットでよく目にするのが見出しのような「〜を鑑み」とするのは間違いである、という主張です。
(例)
炭水化物を控えているのに全然やせない状況を鑑みるに、ロカボダイエットは無駄であると言わざるを得ない。
これはやはり「鑑みる」を「考える」という意味で使っているから「〜を」となるようです。試しに書き換えてみると、
(例)
炭水化物を控えているのに全然やせない状況を考えるに、ロカボダイエットは無駄であると言わざるを得ない。
となり、スッキリ意味が通ります。ですが、
(例)
炭水化物を控えているのに全然やせない状況を照らし合わせるに、ロカボダイエットは無駄であると言わざるを得ない。
と正しい意味で置き換えるとちょっと変な文章になります。「照らし合わせる」と言ってるけど「何」と照らし合わせるのかがよく分からないからでしょう。
実際の使用状況はどうなっているか
ある日本語コーパスのデータベースで検索したところ、「に鑑み」でヒットした例が 197、「を鑑み」の場合は 34 の使用例がありました。
<参考>
コーパス(corpus)とは、言語学において、自然言語処理の研究に用いるため、自然言語の文章を構造化し大規模に集積したもの。(Wikipedia)
私の好きな『ガジェット速報』も「〜を鑑み」が多く登場するサイトです。あらためて「を鑑み」で検索してみたら、100件以上の記事がヒットしました。2月10日には実に3つの記事で使用されています。そのうちのひとつを引用させてもらいます(ひとつの文で2回使われています)。
登場のタイミングを鑑みるに、先日ついに出荷が開始された「Broadwell-U」シリーズの搭載を期待してしまいますが、今回の情報を鑑みるに、あまり過度な期待はしない方が良さそうです。「マイナーアップデート版の新型「MacBook Air」シリーズ、2月24日にも発表か」(ガジェット速報/2015.2.10)
前者の「鑑みる」はやはり間違いでしょうね。ここは「登場のタイミングからすると」程度の意味だと思います。
後者は好意的に解釈すれば使う場面としては間違っていないかもしれません。登場のタイミングからすると「Broadwell-U」シリーズの搭載が期待できるが、今回の情報と照らし合わせて考えると、あまり過度な期待はできない、といったところでしょう。
書き換えれば以下のようになります。
登場のタイミングからすると、先日ついに出荷が開始された「Broadwell-U」シリーズの搭載を期待してしまいますが、今回の情報に鑑みて、あまり過度な期待はしない方が良さそうです。
ちょっとチグハグですね。
文章には硬い・軟らかいという概念があってこれを文章の硬軟といいますが、「鑑みる」という言葉は論文や報告書など硬い文章で使われるイメージが強いと思います。
そこで、「鑑みる」を好んで使う人は格調高い文章に見えることを無意識に期待しているのではないかと思われますが、それが周囲の文章の軟らかさに合わないこともあります。そうすると上の例のようにチグハグな印象となります。
ここは簡単に、
登場のタイミングからすると、先日ついに出荷が開始された「Broadwell-U」シリーズの搭載を期待してしまいますが、今回の情報を見るかぎり、あまり過度な期待はしない方が良さそうです。
とすれば軽くて読みやすい文になると思いますが、いかがでしょうか。